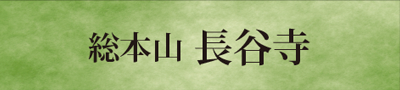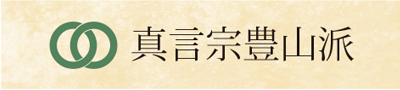おはようございます。
昔の日記を見ていると
その時代の時代を生きている気がします。
6月は忘れていましたが去年は
授戒会を受けていました。
授戒会での思い出は姿勢をとるのが
辛かったと言うのがあったのですが
とても勉強にもなりましたし
お坊さんとしての資質も得られた。
時代を生き抜くと言うのはそういう事
なのかも知れないですね。
でも、大事な事は自分の生きている
事に感謝することであり
自暴自棄になりむしゃくしゃして
人を殺す行為に乗り出してしまうのは
どうかなと思います。
人生が狂う瞬間や何かに戸惑う事など
時代を生き抜くと言うのはそう容易いものでもない。
いじめを受けた少年や
家庭環境の悪い所で育った少年
その時を過ごすと言うのは自分次第であり
学ばなかったのは教えてくれる人間がいなかった
からに他ならぬことだからではないでしょうか?
教育と言う分野を如何に進めるべきかを考えています。
宗教と言う分野には教育を
そして、愛を育むもの与えたい。
争いを起こす事がないように我々に出来る事をする。
それがその時代の時代を生きて行く事である。
平成30年 6月13日 南無大師遍照金剛 合掌
ブログ一覧
お寺とは。
こんにちは。
お寺とは?
宗教とは?
それについて話したいと思います。
お寺の役割は主に暮らしの一部分と思っています。
長い歴史の中で信頼と実績を積んで来た事はどの
ような事かと言いますと。
先ずは、先祖を守護する事の大切さが第一と思っていますし
その他に宿泊施設や場所の提供にも協力されて来ました。
本お寺もコンサート会場として貸し出したりしています。
お寺と言えば頼りになる。だからこそお寺の価値も善かったのです。
しかしながら、現在の傾向を見ますと葬式寺院など
または敷居が高いなど悪い見方もあります。
そういう見方をとってはいけない。もっと別な見方も出来る訳です。
今年の物井の歴史展では多くの方が参加をされました。
四街道市で行われた歴史展示の中で最高の参加人数だったようです。
そう考えてみるとお寺を貸し出す事はとても良い事であるように思います。
また、宗教に関して言えば集団を伴う教えですから
多くの人に衆知し拡散して行く上ではお寺はとても良いと思っています。
特に人々に求められるものは先の見える教え癒しや学ぶ楽しさなど
お寺が人々の憩いの場として癒される場となるように僧侶が実行する事
こそが求められているのではないかと思います。
その上では物井の歴史展示は成功しました。一部の人達には好評は良かったです。
お寺を寄せにする目的も悪くないと思います。
そういう意味でもお寺が努力を重ねて行く事は必然なのかも知れないです。
平成30年 6月14日 南無大師遍照金剛 合掌
仏教に大事な事は。
こんにちは。
今、頭の中で閃いて
このような題を書こう思いました。
役者が即興で作り上げるのと同じで
今、何をするべきかを閃いたなら
それを文章にする。そうではないかと
思います。それでは本題に移りたいと思います。
仏教に大事な事は?
それは救う事だとは思いますが
先ずは人について学ぶ事ではないかと思います。
人というものは先ず感情がある。
感情があるからこそ闘争も起こる。
だから、人を知ると言うのはとても学ぶ事がたくさんある。
人を知らなければ救う術を分からないのです。
では、人とは何なのか?
先ずは欲を持つ者だと言えます。
欲望を持つ事には障害が伴う訳ですが
欲がなくては生きていけないとも言えます。
だからこそ、多くのもなく少なくもなく中間が善い
とされる思想もある訳です。
般若心経の不増不減などはそのような意味
なのかも知れないですね。
そのように仏教には正しい教えが詰まっています。
平成30年 6月14日 南無大師遍照金剛 合掌
法を弘める。
おはようございます。
今日は雨模様です。
そして、弘法大師空海さまの誕生日です。
大師の諡を貰った年は延喜21年(921年)10月27日
東寺長者観賢(かんげん)の奏上により醍醐天皇から
頂きました。当初は本覚大師の諡号を贈られるように
なったが「弘法利生」の業績から弘法大師の諡を貰ったので
あります。その本覚大師は後に益信僧正に受け継がれ
広沢流の寺院である仁和寺や大覚寺といった有名寺院
輩出しました。このような事から法を弘めた業績を頂いた
訳なのです。また、もう一つ別の名前があります。
それは遍照金剛です。これは、真言宗の秘密の儀式で
ある灌頂(かんじょう)を受けた際にどの仏さまと縁を結ぶかの
時に空海さまは大日如来と縁を結んだのです。
その為に「この世の一切を遍く照らす最上の者」である
遍照金剛の灌頂名を頂きました。
平成30年 6月15日 南無大師遍照金剛 合掌
宗教とは何なのか?
こんにちは。
今日のお題は宗教学について。
一昨日の土曜日は神奈川県の八景島に近い
龍華寺さんを訪れました。
その中で密教はとても分かりずらい。
宗教の話が人々には受け入れやすいとの事でした。
お坊さんの見解では
密教は方便であり、宗教の立場で話をしたら
聞いている人には分かりやすい。
そんな私は仏教の基本となる話を法事の時にしました。
四苦八苦についてです。
仏教の基本となる苦について
皆さんはどのように受け止めていますか?
仏さまの教えの基本は苦を滅する所から
始まります。その苦には四つから八つあると言います。
その四つとは生・老・病・死と言います。
すなわち、生まれて来る時の苦しみ
老いを感じる時の苦しみ
病を患う時の苦しみ
死を感じる時の苦しみ
苦しみにはそれぞれ意味があります。
その苦を滅する所から仏教を理解出来ると言います。
苦を別の見方で煩悩と表現で言ったり無明と言う言い方で
言います。無明とは明かりが無いと書くごとく真っ暗な闇を意味します。
私たちは光の基に自分を確かめながら生きています。
その光の明かりが無かったのなら何を頼りにして良いのか
分からなくなります。自分の想い通りにいかない。まさに苦です。
私たちの生活の中でも苦は伴っています。
その基本が四苦と言う事です。この苦をどのように滅するのか
を説いたものが仏教の教えです。
今日はその実践として読経のお勤めをさせて頂きました。
声に出して仏さまの言葉を出す事により
私たちは安心な心で向かい合う事が出来るのです。
少し法話を加えていますがお話はこのようなものです。
できるだけ、話はわかりやすくする必要があります。
平成30年 6月18日 南無大師遍照金剛 合掌
お寺と檀家のつながり。
おはようございます。
今日は快晴です。
だいぶ夏らしくなって来ました。
一日一日を大事に生きて行きましょう。
今日のお題は「お寺と檀家のつながり」について
お寺とは何か?檀家とはどうあるべきか?
それについて皆さんは明確に知る必要はあると思います。
お寺にお渡しするお布施とは何か?
お布施とは何度も言うようですがダーナの事で
他人に対して財物を施したり、相手の利益になるような教えを説く
事を言うのです。
その中で前者のダーナを檀家の役目の事を言い。
後者のダーナをお寺の役目だと感じる訳です。
互いに強いつながりを築く為にはこの関係をより良好に
する必要があるでしょう。
昔のお寺さんは座って飲んでいれば良いと言う感じだったようです。
お寺さんによっては違う感じかもしれませんが
お坊さんのお寺はお寺に行けばお酒が飲める。
話し合いの場でもあり。いわゆる公民館がわりの
ようなものでもあります。
これは善い方と受け止めて良いのか悪い方と受け止めて良いのか?
それについても今後協議する必要のある問題です。
平成30年 6月19日 南無大師遍照金剛 合掌
弘める心。
こんにちは。
今日はお日柄も良く快晴です。
お盆の季節が近づいています。
少しずつ弘めて参りましょう。
今日のお題は弘める心です。
流布と言う言葉もありますが
全体に流れるように弘める意味があります。
この所は仏教の活躍は御朱印帳のようなものですが
出来ればそれ以外の場でも活躍の場が見せられれば
良いです。そもそも仏教の醍醐味とは如何なるものか?
抜苦与楽。転禍為福。武者修行。
元々は福や修行と言った目的の中で
育まれたものが仏教であったと言えるのです。
弘める。福や修行と言ったものを。
お坊さんは実践行をすすめたいとは思っています。
平成30年 6月25日 南無大師遍照金剛 合掌
知識を深める。
おはようございます。
今日のお題は「知識を深める」と言う事で
話を進めて行きます。
お坊さんも今本を読んでいます。
仏教の本ではなく小説です。
読みやすい本を読む。
本を読んでいくといろんな発見が見える
と思います。書き手によって
本の内容の情景も違います。
本は文字だけのもの絵と共に
綴られているものがあります。
お坊さんが読んでいる本は文字だけの
本です。想像力が養われると思います。
文字を追って行く内にここはそうだろうな
とか舞台はこうだとか音楽まで感じて来ます。
それだけではなく本が伝える知識まで得られます。
最近のお坊さんの心境は本を読む事でした。
ここ何年かは本を読む事に億劫でした。
でも、なぜか読む事に飢えています。
人間は知識を取り入れることを好むのだと分かる事。
人間は話す事も好きだ。
話題もなく何一つ変化もなく。
そんな生活をして行くうちに変えたい自分が現れる。
本が変えていく。知識を深め今までの自分を変えよう。
平成30年 6月28日 南無大師遍照金剛 合掌
過去への未練は?
おはようございます。
長い事更新が滞ってしまい申し訳ございません。
7月に入りお盆の打ち合わせもしなくてはなりません。
さて、更新がなかった間を報告すると
6月の28日は真言宗豊山派千葉県布教師会がありました。
会場は三井ガーデンホテル千葉でした。
会計監査報告後は布教師会規則の改正について話されました。
その後は研修会を行い「仏教(菩提寺)に対する檀信徒の意識」
と題して真言宗智山派智山教化センター山川弘巳先生の講演
を聞きました。
その後は7月1日は円福寺の下水道の泥を取り除くどぶさらい
を実行しました。多くの方に協力を得られて助かりました。
今日のお題は「過去への未練は?」と題しまして話していきます。
私たちは生まれてから今日まで自分のために他のために生きていきます。
それは自然の流れのように思います。その中でこうしていけば良かった
あーしたら良かったなど未練を残す事があるでしょう。
お坊さんは想う事があります。自分たちは生きるだけで精一杯の人も
いますし何一つ力が及ばなかった。悔いがあるのなら自分が出来る事
をするべきかと思います。よく思い出す言葉があります。
自分が生かされている意味を知るべきだとお坊さんはこのように
思います。仏教が檀信徒から離れて行く傾向など危惧される
恐れはないと思います。そうさせてはいけないんだと気持ちを
全面に出すべきだと感じるのです。自分の出来る事を先ず
始めましょう。
平成30年 7月3日 南無大師遍照金剛 合掌